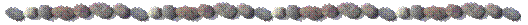| 増田光一 旅行記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「日本で考えたこと、西欧で見たこと」 増田 光一 巷では「スピリチュアル…な世界」が何かと騒がしい。マスメディアに常に扇動される日本人らしいが、死生観がブームになること自体どこかおかしくないだろうか。一昔前、大ブームになったUFOのように、「前世」や「死後の世界」は単なるお伽話として直に忘れ去られていくような気がする。それにしても、日本人とは昔からこんなに即物的に生きてきたのだろうか。どうしても僕にはそう思えない。なぜなら、成熟した巨大な芸術がいつの時代も日本には存在していたからだ。運慶、快慶の彫刻はどう見てもミケランジェロのそれに劣らない。戯作者によって書かれた黄表紙の世界に含まれる哀しさはO・ヘンリーに比べて浅いと思えないし、源氏物語の人間描写はシェイクスピアに見劣りしない。見劣りするどころか、細やかな心情を描き出すことにおいては秀でているのではないだろうか。北斎、写楽、歌麿の浮世絵は肖像画の天才モディリアーニに比べどうだろう。僕なら自信を持って江戸の三人に軍配を上げる。おそらく彼らは自分が天才であり、努力で這い上がろうとしている哀れな人間とは別次元の存在であると分かっていたはずだ。僕の浅い知識の中で断定するのはいささか気が引けるが、そういう人間達を許容する、もしくは積極的に受け入れる社会があったということが現在と大きな違いなのではないだろうか。文化を楽しむ、ひいては人生を楽しむ風潮が色濃く存在していたように思う。もちろん、今でも文化、芸術に対して真摯に心を開いている人も居るが、僕にはいろいろな意味で、そういった人達は偏った中にしか居ないように思われる。文化、芸術は実体として存在しないものが根底にあり、それを受け入れないと何のことやらまったく分からない。大体芸術とは「おばけ」や「UFO」を信じない人種には理解できないものだ。芸術活動とは人智を超えたところに存在する「何か」に近づこうとして、もしくはその真似をしようとする行為だから、「あの世」とか「神様仏様」を信じない人達に理解できる筈が無いのだ。「おばけ」を恐れ、浄瑠璃に涙した江戸時代の日本人のなんと豊かなことか!そんな時代の人間から見れば当たり前なことである「スピリチュアル…な世界」に感心するとはどうしても思えないのだ。
その年の夏に僕は家族と南フランスに旅行に行くことにし、いつもの通りにホテルの手配をしていた。最初の宿泊地は行程の関係上リヨンにした。リヨンは大きな町で旧市街地、新市街地(といっても町並みの建物はほぼ100年前のものだった)ともに沢山のホテルが存在している。同行する家内の母の足が不自由なことを考え、いつも市内の便利な場所に建つホテルを選んでいる。リヨンのホテル照会サイトを自宅のパソコンで見ていた僕は一つのホテルの写真を眼にした。それはおそらく100年程前の建物で、貴族の館であったろうファサードをしていた。国鉄リヨン駅すぐ脇に建っているらしく、行こうとしている旧市街地へは地下鉄を利用しないと行けないことが案内で解った。写真では周りに建物が無く、ぽつんと立っているのが不思議に思えたが、僕は左程迷うことなく何故かそこを予約した。海外旅行のホテルの予約をする時の事などほとんど、というよりまったく覚えていない僕だが、この時のことはよく覚えている。……何故だろう?今思うと何故僕はあのホテルを選んだのか不思議でならない。
さて、そのリヨンに着きホテルに入った時の事も、僕にしては珍しく事細かく覚えている。ロビー、部屋は天井が高く広かった。窓を開けると旧市街地や丘の上のフルヴィエール教会が左奥に見えなかなか良い眺めだったが、どこか平凡な景色に感じた。その眺望を僕は何回かカメラに収めた。 このときの旅行は南フランスの眩いばかりの白壁と、圧倒的な陽光に彩られた美しい想い出となり、リヨンのそのホテルの影は脳裏にかすんでいった。 その年の年末、僕と家内は深夜にふと目覚めた。所在無く何気なく点けたテレビで、たまたまナチスのドキュメンタリーをやっていた。占領されたフランスにおいて、フランス人ナチス将校がいかに残虐であったかを当時を知る証人が物語る、というおよそ年末にふさわしくない番組であったが、僕たちは知らずそこに引き込まれていった。その将校の本拠地がリヨンであることを語り始めたからだったが、僕たちの度肝を抜いたのは、その後映し出されたリヨンのナチス本部と紹介された建物を見たときであった。それはまさにその年、僕たちが泊まったホテルに間違いなかった。さらに、将校がユダヤ人を尋問し処刑の決定を行っていた部屋から見た風景が画面に現れ、それを見た僕たちは絶句し画面に釘付けになった。僕が何度も撮ったあの平凡な風景がそこに映っていたからだ。 「これは、何だろう。僕たちに、誰が何を言いたいのだろうか……。」 ホテルを予約したときから始まり、たまたま見かけた深夜のドキュメンタリー映画に至るまで、僕たちに何かを意識させたい、という一貫した意志が働いているようにしか思えなかった。これは偶然ではなく必然なのではないだろうか。 親の影響もあってか、子供の頃から僕は第二次大戦下のヨーロッパ、特にナチスドイツに対し強い関心を持っていた。集めているつもりではないが身の回りに関係書が多く、読み返すたびに血が逆流する程の恐れと、行き場の無い悲しみに一人泣くこともあった。前世で何かあったのでは、と思い始めたのはそれほど昔のことではないが、そう思い始めてから何か合点の行くことが多い。音楽もそうだ。僕の前世はそのあたりと何か関係しているのだろうか。家内と前世の話をたまにするが、どちらかがナチスでどちらかがユダヤだったのではないかとよく揉める。もしそうなら僕はナチスでは無かったような気がする。理由は無いがそんな気がする。家内もそう思っているらしく、前世で苛めた分、今苛められている、等と言っている……。その後はどういう訳か、家族での旅行は圧倒的にフランスが多い。僕の、そして僕の家族の何かが、そうさせるのだろうか? そういえば、よく見る夢の街並みが西欧のそれによく似ていることが最近わかった。その街は簡単な地図を描くことも出来る程本当に夢によく現れ、その町にある自分の部屋の間取りも描ける。白い壁であまり物は置いていないが、窓際にいつもキャンバスが置いてある。自分で描いているのかは分からない。20畳ぐらいはありそうな部屋だ。リアルであるし、よく見る夢なので目覚めたときに夢か現実か混乱することがよくある。しかし、よく考えてみればどこからが現実でどこからが夢だとはっきり言える人間なんて居ない筈だ。こういう夢を見た後はとくに、ここに居ることがおそらく夢であるような気がしてくるし、実際そうかもしれない。「色即是空 空即是色」とはこういうことなのだろうか。だから何だ、と言われればそれまでだが、僕たちの前には未知の世界が広大に広がっているのは事 実だし、もしかしたらそれらの事は僕の中で簡単に片付けられない事かもしれない。
僕にとって夏に海外に出掛けることは何にも増して大きな楽しみの一つになっている。以前はウィーン、パリ、ローマ、ミュンヘンなど大きな都市に出掛けることが多かったが、この10年位は専ら田舎の小さい街に行くことにしている。理由の一つには、聴くべき演奏会、オペラが無いことがあるが、それ以上に戦火を免れた中世さながらの美しい街並みにゆったりと身を置くことの喜びは何物にもかえられない。最近はフランスの田舎に行くことが多いが、どんな田舎でもフランス料理をしっかりと楽しめる店があるのが嬉しい。なんでもパリの料理店の価格が上り、優秀なシェフが地方に流出しているからだそうだが、僕たち旅行者にとって何よりだ。もう一つの楽しみはワインだ。量を飲めない僕はグラスで頼むが、中にびっくりする位の値段がついているものがある。その地方の特別の逸品だ。これを飲みながらの現地フランス料理は最高で、このまま時間が止まっていてほしいと心底思う。最高のオペラにどっぷり浸っている感じだ。更にどんなに酔ってもホテルは眼の前。相当怪しくなっても何の心配も無いのが良い。田舎町の人達は僕たち東洋の旅行者にとても優しい。というより、珍しくて興味があるようなのだ。パリやローマではブランド品漁りに我物顔で闊歩する日本人達が本当に嫌われている。田舎の人たちはそういう部分をあまり見ていないからだろう。第二次世界大戦時、カンボジアで日本兵に右腕を吹き飛ばされたという老人までも、抱きつかんばかりに受け入れてくれた事もあった。毎日、作務衣や浴衣でぶらぶらしているものだから、町のみんなにすぐ覚えられてしまう。絵を描いていると必ず隣に誰かが座って話しかけてくる。そうでなかったことは1回しかない。そこは牛以外、誰も居ないところだったから仕方ない。そんな風にしていると、本当にここは自分の居るべき処なのではないか、と思えてきたりするのだ。 僕が旅行した所でお勧めの街、村を紹介しよう。先ずはフランス。街並みの美しさ、料理、ワインと3拍子そろった街はアルザスのコルマール。近くのストラスブールより小さいが、この街のあまりにも優雅な時間の流れが僕は好きだ。中世を感じさせる外観の見事さと豪華さで雑誌の表紙にもよく載るホテル・マルシェルは料理の見事さで有名だ。
パリより美味しいと定評のディナーはまさに夢を見るような食事だった。こんな小さなホテルにシラク前大統領をはじめとする政府要人、多くの著名演奏家が常連なのも分かる。
一品一品がどれも涙が出るほど美味だったが、きのこのソースをかけたほろほろ鳥の複雑な味わいは忘れられない。頼んだグラスワインはアルザスの銘酒。ジュースのような甘みとトロとした感覚にびっくりしたが、これが料理にぴったりだった。 コルマールから車に乗り30分程で、アルザスワインの生産地の一つ、リクヴィールという小さな村に着く。この村の裏手にあるブドウ畑の丘の上から見下ろす村の美しさは格別だ。丘を登りながら盗み食いした葡萄の美味しかったこと!行った2003年は大猛暑で、(と言っても日本より遥かに涼しい)この年製造のワインは近年稀に見る上物と定評がある。
リクヴィールの近くにリボーヴィレ、エギスハイムというとても似た村がある。リクヴィールに比べ、リボーヴィレは商店などが揃い、僅かに近代の匂いがする。そういえば、フランスの小さい村には店がほとんど無い。みんなどこで生活用品を買っているのだろう。地味だがエギスハイムの街並みの落ち着いた美しさも特筆に価する。
同じ3拍子でもワイン好きには堪らない街はブルゴーニュのボーヌ。
ここの居心地の良さは格別だ。街並みの美しさはもとより、どこの道を歩いてもワインカーブがあるのが素晴らしい。3〜5ユーロほど払ってカーブに入れば飲み放題である。現地のつわものはフランスパンを一本小脇に抱え、それを毟りながらひたすら飲んでいた。銘酒シャンベルタンを存分に飲める、本当に贅沢な街だ。最高級ホテルはル・セップ。このホテルの料理も折り紙つきで、フランス料理人でここを知らない人は居ない。泊まっていても予約をしていないと入れない!注文してから待つこと2時間、あまりに美味しい肉料理に思わず笑いが出てきたものだった。カトリック巡礼の基点ヴェズレーの神秘的なロマネスク様式教会の美しさ、絵本から出てきたように幻想的に丘に立つスミュール・アン・オーソワの景観も忘れがたい美しさだ。
何と、この2枚の写真で街の建物のほとんどを網羅している。周りはどこまでも続くブドウ畑だ。細い路地に普通に構えているレストランがこれまた美味しかった。
プロヴァンスは大きな町でも素敵だ。何といっても日光の輝きが違う。多くの画家を惹きつけたその明るさは街の景観を一際際立たせる。僕の好きな街は、アヴィニョン、アルル、タラスコン。それぞれが違った個性を持っている。アヴィニョンは整然とした美しい町だ。元法王庁の壁の白さは眩いばかりで当時の権力を彷彿とさせるが、黄昏時の哀しい美しさは筆舌に尽くしがたい。ローヌ川岸のベンチに老夫婦やカップルが夕陽に映え刻々と変化する法王庁を静かに眺めている。漣の音だけがいつまでも微かに響き、誰もが黄昏に浸っていたのが印象的だった。夜はしっとりとしているが、南仏の活気がある。移動遊園地でメリーゴーランドに乗ったが、切る風の爽やかさが本当に気持ち良かった。ここも食通が集まる街だ。
タラスコンは起源を江戸小紋と同じくインド更紗とするプロヴァンス・プリントで有名だということを行ってから知った。朝は市場に屋台が溢れ、活気に満ち溢れていたが、印象的だったのは昼下がりのシエスタだ。太陽に隈なく照らし出された街並みから魔法の様に人が消え、たまに道を横切るのは猫だけ。その静寂は「時間が止まった町」を絵に描いたような光景だった。また、タラスコン城上から見る家並みの景色は秀逸だった。
ゴッホ、ピカソなどの画家たちのみならず、ビゼー等の音楽家もその魅力の虜になったアルルは古代遺跡の上に建った力漲る街だ。ラテン気質と言おうか、街行く人の表情が明るく、心なしか声も大きい。気持ちのいい街だ。今も利用されている闘牛場は石造りのローマ時代遺跡、よく見るとそこここに悪戯書きが彫られている。相当の労力だと思うが、昔から善からぬ人が居るもので、1800年代の物も結構ある。闘牛場から見下ろす街の景色は素晴らしかった。ここの屋根も平たく、街の古さを物語っていた。
ドイツにも是非見てほしい街がある。僕が「住みたい」と思ったのは、古城街道のシュベービッシュ・ハルだ。どこを取っても絵の様に美しい街並み、町の中心部でも見事な天の川が見られるほどの透明な空気。とても小さな町だが居住環境も素晴らしいと思った。古いが活気ある商店街があり、美術館やシェイクスピア劇場(当時の劇場を復元!)まである。町の中央に流れる小川には小鳥が戯れていて憩いの広場になっている。住んでいる人が羨ましい!
僕の泊まったホテルは町の中央、協会脇にあったが、ここのオーナーが兎に角人が良く、何かお礼をすると何倍にもなってサービスが返ってくる。ある夕食時、日本の切手をプレゼントしたお礼に、オーナーの奥さんがニコニコしながらここの名物料理の肉団子(直径15cmくらいある)を、どかどかと僕の家族の皿に入れてきた時は、本当にどうしようかと思った。とっても美味しいがこれを一つ食べると、僕のお腹ではもう何も食べられないからだ。
ハルツ地方で僕が大好きな街はゴスラーとヴェルニゲローデだ。共に裕福な中世時代を経てきたと思われるが、街の雰囲気はまるで違う。建設当時から競うようにファサードが美しく彩られ、往時の繁栄を今に色濃く残しているのがヴェルニゲローデだ。同心円状に街が広がっていった様子が歩くとよくわかる。最外周の家々の木組みも美しく絵にならないところが無い。また、この街はSLでも有名で操車場には良く手入れされたSLが現役で働いていた。僕は嬉しくなって勝手に操車場の中に入り、間近に触れてきた。(駅員が笑ってそれを許してくれた)傍によって見ると正面のプレートが僕のほぼ眼の高さにあり、日本のSLに比べると可也小さく可愛い感じがする。今度行ったときは是非乗ってみたい。
ゴスラーの町に入ると、その重厚な雰囲気に飲み込まれる。教会の鐘楼から街を見下ろすと、その深く落ち着いた空気の理由がわかる。屋根のスレートがグレーに統一されているのだ。街全体の基調はモノトーン、これにレンガ色が加わり、これこそドイツ、という顔をしている。バッハの音楽を聴いているようで、僕はすぐに気に入ってしまった。写真左の赤い建物はホテル・カイザーヴォルト。500年の歴史を持つ。ここの部屋、そして食事は良かった。ドイツでこんなに美味しいと思ったのは珍しい。
2006年の旅行で初めて行ったバーデンは本当に素敵な大人の街だった。モーツァルトも縁あるが、何と言ってもここはベートーヴェンが第9を書いた所なのだ!街は温泉地らしく草津のように硫黄のにおいがする。家は殆どが2階建てで色調も統一されている。オーストリアにこんな素敵な街があるとは一寸驚いたものだった。
僕にとって、ベートーヴェンは特別な存在だ。第9を書いた家に入るなど、まさに夢以外の何物でもない。「ここで…、この窓から外を見ながら…、この階段を上って…、あの道を歩いて…」彼はあの不滅の金字塔をうちたてたのだ。
2007年から2008年にかけて、アンサンブル凜では弦楽四重奏曲14番を、SAKURAでは第9に取り組むという一生に何度も無い幸せを得、年男の僕にとって特別の年になった。2年間、僕は肌身離さずスコアを持ち歩いていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||