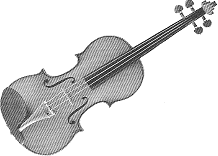≪オーケストラの楽器≫その2 神秘性の権化一ヴァイオリン 岩井倫郎
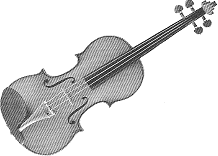
ヴァイオリンという楽器について何か書くということは、つづまるところ、ヴァイオリンの名器の音の秘密は分からぬということと、1700年ころから約150年の間に作られたイタリアの名器への憧憬と羨望の念を書くことに外ならない。イタリアの名器としては、ストラディヴァリ、グワルネリを頂点とした、古くはアマティからロジェーリ、ベルゴンツィ、ガリアーノ、マジーニ、グァダニーニ、グランチーノ等、一連の作家のものを指す。
大体ヴァイオリンを弾いている者にとって、今自分の使用している楽器に満足しているのは少数である。自分に合ったもっと相応しい、楽に音が出せるすぐれた楽器があるはずだと常にその価格とのバランスで目を光らせているわけである。また、自分で弾く自分の楽器の生の音を客観的に聴くのは不可能なのであるから、ヴァイオリン弾きというのは常に自分の楽器に不安をもっているものである(自分の技術の未熟さを棚に上げて……)。そもそも自分の音がどれほど鳴っているか、質はどうなのか分からないのだから、不安解決の方向を求める。その方向はイタリア18世紀の作品に向けられるというわけである。
こうしたイタリアの名器の美しい音色の謎については、科学者の手によって、デザイン、音響学的特徴は数学的に解明され、曲線の青写真も完成している。しかし、世界的権威であるレンバート・ワーリッツァーの言うように、「すぐれたヴァイオリンはクレモナ中心に作られたが1740年代の頃より後に、これら偉大な楽器の桁外れの演奏性と音に太刀打ち出来たものは一つもない。今日に至るまでその理由は謎であり、演奏家もヴィルトゥオーゾも、200年たった今もなおクレモナの素晴らしいヴァイオリンを捜し求めている」のである。
イタリアの名器について科学的解明はある程度なされたが、再現は不可能といった混沌の中で、その秘密は何かということについて、私のごとき浅学の徒が云々するのは恥ずかしいことこの上ないが、何年か自分なりに弾いてきた立場から感想として言うならば、第一には木材の材質であろうと思う。表は松、裏板はカエデであるが、松は南スイスとチロルの山間の南斜面に成育するものであり、カエデはクロアチア、ダマルディア産のものであるという。ニスをかけることによって、これらの木目は見事な模様を浮き上がらせ、表板のやや間隔の開いたまっすぐな目、裏板のいかにも粘り強く硬い引き締まった質感を表出する。この木目による材質の判断が最も優先する。さらに材質を判断するに当たって、手に感じる不思議な重さというものがある。これは「重量」ではなく「重感」とも言うべきものであり、質感と相挨ち、さらに楽器全体の部位の重さのバランス感も加わって一種の個体としてのまとまりを持つ者に伝える。これは逆に言えば、「不思議な軽さ」とも言えるのであって、名器を手にした瞬間先ず感じるのはこの軽さと、人体への密着感である。ただし例外もある。イタリアではないが、フランスの名器ヴィヨームを少しの間使ったことがあるが、これは音量豊かでいい音が楽に出せるものの、「洗面器」といったようなまことに平らで大きなヴァイオリンであった。次には、楽器のつくり、形状であろう。イタリアの名器グランチーノとカミラス・カミリの二つの楽器に共通するのは、見事な胴の厚さである。まことにグラマラスである。グランチーノの素晴らしい音質、カミラスの弓を跳ね返すほどの力強さはこの胴の立体的厚さから来るものではないかとも思われる。しかし、胴の厚さにしても一概には言えず、音量の増大を図るために平らに設計したグァダニーニや前述のヴィヨームの例もある。要はヴァイオリンという楽器(箱)の容量を基にした厚さと面積のバランスであろうか。ニスについてはその美しさの魅力がさらに神秘性を増大させる。「ヴァイオリンに関してニスほど不思議なものはない」(ヨゼフ・ヴェクスヴァーグ)のであるが、ニスは湿気の予防とともに、木の目を強調させる働きがあり、ニスをかけることにより結果的に、こうした木目なら良い昔が出ると判断したのではないかとも思われる。しかし音の美しさとニスの美しさは同一視せざるを得ないほど、ニスの色は魅カ的である。
色々と勝手なことを書いたが、結局、ヴァイオリンというものの論議はすべて結果論であって、こうすればこうなるというものでは有り得ない。現在イタリアの作家によって作られた作品が1世紀を経て、ストラドのように価値を認められるかも知れないが、それも結果を見なければ分からぬのである。それでも私たちは名器にあこがれ、賛美し続ける。
 愛響ア・ラ・カルトへ戻ります。
愛響ア・ラ・カルトへ戻ります。
 ホームページへ戻ります。
ホームページへ戻ります。